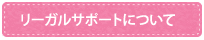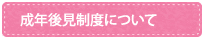法定後見とは?
成年後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が不十分な状態にある場合、本人の財産や権利、ひいては「命」を法的に守り、本人が自分らしく生きることを支援する制度です。
本人と支援する人との契約によって成立する「任意後見」に対し、親族等の申立により家庭裁判所が後見人等を選任する制度を「法定後見」と呼んでいます。ここでは「法定後見」についてご説明します。
「法定後見」は、本人が有している判断能力の程度によって、| 『 | 後見(こうけん) | 』 |
| 『 | 保佐(ほさ) | 』 |
| 『 | 補助(ほじょ) | 』 |
の3類型に区分され、後見人等の権限や職務の範囲に違いがあります。
この3つの区分は、専門用語のため一般の方々には少々なじみにくいかもしれませんが、さらにわかりやすく言えば、認知症や障がいなどによる判断能力の減退の程度により、その程度が| 重度の場合 | ⇒ | 後見 |
| 中度の場合 | ⇒ | 保佐 |
| 軽度の場合 | ⇒ | 補助 |
と捉えていただければご理解いただきやすいと思います。
後 見
後見は、精神上の障がいにより判断能力を欠く状態にあることが通常である方を対象としています。これは、自分の財産を自ら管理・処分することができない状態、具体的に言うと、例えば
「日常的に必要な買物すら自分でできず、誰かに代わってやってもらう必要があるといった程度の状態」
を指します。
後見開始の審判によって、後見人は、本人に代わって財産の管理や様々な契約締結などの法律行為をしたり、また必要に応じて本人が単独でした法律行為を取り消して、本人の生活を全般的に援助します。
保 佐
保佐は、判断能力が著しく不十分な状態にある方を対象としています。これは、自分の財産を管理・処分するには常に援助が必要な状態で、具体的に言うと、例えば、
「日常的な買物は自分でできるが、金銭の貸し借りや不動産の売買等の重要な財産行為については自分ではできないといった程度の状態」を指します。
保佐開始の審判によって、本人が一定の重要な法律行為(民法第13条第1項に定める法律行為)をするには、保佐人の同意を得ることが必要になります。なお、保佐人の同意を要する法律行為は、家庭裁判所の審判によって追加することもできます。【※注1 末尾参照】
保佐の場合は、後見とは異なり、本人が一定の判断能力を有している状態にあるので、保佐人には、原則として本人の財産の管理や法律行為を本人に代わって行なう「代理権」はありませんが、本人の同意と家庭裁判所の審判によって、ある特定の法律行為について保佐人に「代理権」を与えることもできます。【※注2 末尾参照】
保佐人はその定められた権限の範囲内で本人のしようとする法律行為に同意したり、ある法律行為を代理したり、また、必要に応じて本人が保佐人の同意を得ずに単独でした法律行為を取り消すことで、本人が財産を減少させたりすることを防ぐ等により本人を援助します。
なお、「代理権」に関しては、保佐人等の権限が必要以上に過大にならないように、本人の生活支援等に必要な最小限の範囲のみ与えられるのが裁判所実務での傾向です。
補 助
補助は、判断能力が不十分な状態にある方を対象としています。これは、自分の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある状態で、具体的に言うと、例えば
「日常的な買物は自分でできるが、金銭の貸し借りや不動産の売買等の重要な財産行為については自分でできるかどうか危ぶまれる程度の状態」を指します。
補助の場合、本人以外の方が補助開始の申立てをするには、本人の同意が必要となります。また補助開始の審判とともに、補助人の同意を得なければならない法律行為の範囲か、もしくは補助人が本人に代わって法律行為を行なう代理権の範囲が定められますが、この定めをするにも本人の同意が必要です。【※注2 末尾参照】
補助人の同意が必要な法律行為の範囲も保佐よりさらに限定され、民法第13条第1項に定める法律行為の一部に限られます。【※注3 末尾参照】
いずれも本人が保佐の場合よりも判断能力を有している状態にあるので、本人の意思を尊重する趣旨からです。補助人はその定められた権限の範囲内で本人のしようとする法律行為に同意したり、ある法律行為を代理したり、必要に応じて本人が補助人の同意を得ずに単独でした法律行為を取り消すことで、保佐と同様に本人が財産を減少させたりすることを防ぐ等により本人を援助します。
同意権や代理権については、以上のご説明のみでは具体的にイメージしづらいかもしれませんので、実際の裁判所への申立手続等において使用されている同意権や代理権の具体的な内容について、本ページ末尾に参考に例示しておきます。
実際の後見制度の利用においては、ご本人のご希望や生活状況などを踏まえて具体的な内容を決定しますが、どういったことを保佐人等に任せることができるのか等についてご検討される一助になれば幸いです。
共通点
以上のように、後見人・保佐人・補助人が取り消すことのできる法律行為の範囲は、法定後見の類型ごとに違いがあります。
ただし、取引の安全を保護する観点から、日用品の購入等の日常生活に関する行為については本人が単独でした場合であっても、後見人・保佐人・補助人ともに取り消すことができません。
また、後見・保佐・補助いずれの類型においても、後見人等が職務を行うに際しては、本人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮することが求められています。
これらは、成年後見制度が、本人が自分らしく生きることを支援する制度であるためです。
| 1 | 貸した土地、建物、お金を返してもらったり、これらを他人に貸したり預けたりすること。 |
|---|---|
| 2 | お金を借りたり、他人の保証人になること。 |
| 3 | 不動産や高価な財産を売り買いしたり、貸したり、担保をつけたりすること。 |
| 4 | 訴訟を起こしたり、訴訟を取り下げたりすること。 |
| 5 | 贈与、和解をしたり、仲裁契約をすること。 |
| 6 | 相続を承認、放棄したり、遺産の分割をすること。 |
| 7 | 贈与や遺贈を断ったり、何かを負担することを条件とした贈与や遺贈を受けることを承諾すること。 |
| 8 | 新築、改築、増築または大修繕の契約をすること。 |
| 9 | 宅地を5年以上、建物を3年以上、動産を半年以上にわたって貸す契約をすること。 |
(参考URL)http://www.courts.go.jp/nara/vcms_lf/20203002.pdf
| 代理行為目録 | |
| A | 財産(預貯金を除く)の管理・保存 |
|---|---|
| B | 財産(預貯金を除く)の処分・変更
|
| C | 預貯金の管理(口座の開設・変更・解約・振込・払戻) |
| D | 貸金庫・保護預かり取引に関する事項 |
| E | 定期的な収入(賃料・年金・配当金等)の受領及びこれに関する諸手続 |
| F | 定期的な支出を要する費用(賃料・公共料金・保険料・ローン返済金等)の支払い及びこれに関する諸手続 |
| G | 本人が負担している債務の弁済及びその処理 |
| H | 遺産分割又は相続の承認・放棄 |
| I | 保険に関する事項
|
| J |
証書等の保管に関する事項
|
| K | 介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項
|
| L | 医療(病院への入院を含む)に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払い |
| M | その他の事項 |
| N | 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項(示談、訴訟行為、弁護士への訴訟行為の委任等) |
| 同意行為目録 | |
| 1 | 元本の領収と受領
|
|---|---|
| 2 | 借財又は保証
|
| 3 | 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
|
| 4 | 訴訟行為 (相手方の提起した訴え又は上訴に対して応訴するには同意を要しない。) |
| 5 | 和解又は仲裁合意 |
| 6 | 相続の承認若しくは放棄又は遺産分割 |
| 7 | 本人が負担している債務の弁済及びその処理 |
| 8 | 遺産分割又は相続の承認・放棄 |
| 9 | 民法602条に定める期間を超える賃貸借 |